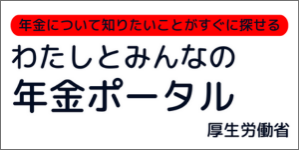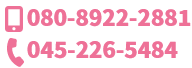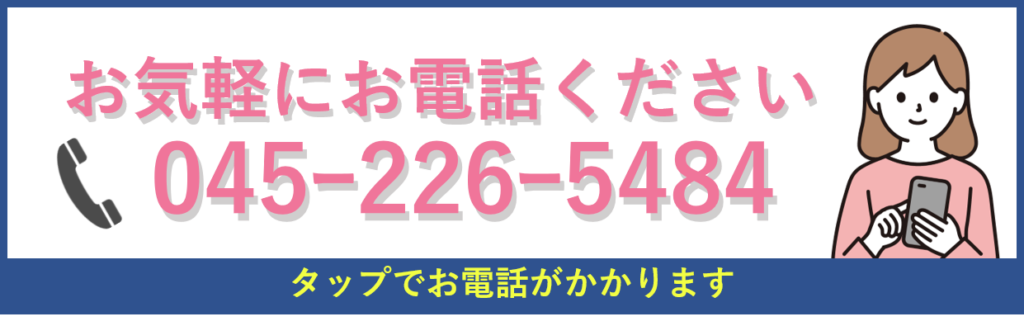障害年金併合認定申請の手続きと必要書類
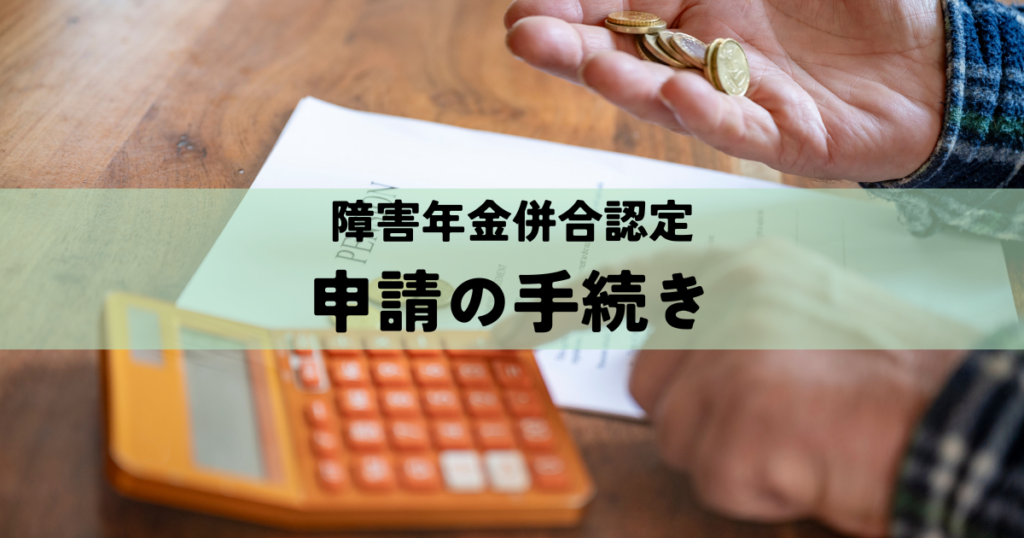
複数の障害を抱えていると、障害年金の認定が複雑になります。
一体どのような方法で認定されるのでしょうか? 申請に必要な書類は何が必要なのでしょうか? 不安を抱える方も多いのではないでしょうか。
今回は、複数の障害を持つ場合の障害年金認定方法の一つである「併合認定」について、申請に必要な書類や手続きを分かりやすく説明します。
スムーズな申請に向けて、ぜひご活用ください。
障害年金の併合認定とは
併合認定の定義と種類
併合認定とは、複数の障害を個別に評価し、それぞれの障害の重さを総合的に判断して、最終的な障害等級を決定する方法です。
複数の障害を持つ方が、それぞれの障害を個別に申請するよりも高い等級に認定される可能性があります。
併合認定以外にも、加重認定、総合認定、差引認定といった複数の障害に対応した認定方法があり
ます。
加重認定は、既に障害年金を受給している方が新たな障害を負った場合に適用されます。
総合認定は、複数の障害が複雑に絡み合い、個別に評価できない場合に用いられます。
差引認定は、既に存在する障害(前発障害)と同一部位に新たな障害(後発障害)が生じた場合に、前発障害の程度を差し引いて後発障害の程度を評価する方法です。
併合認定の仕組みと流れ
併合認定では、主に「併合判定参考表」と「併合(加重)認定表」を用います。
まず、併合判定参考表に基づいて、それぞれの障害に番号を割り当てます。
この番号は、障害の程度を表しています。
次に、これらの番号を併合(加重)認定表に当てはめることで、最終的な併合番号が算出されます。
この併合番号から、障害等級が決定されます。
2つの障害がある場合、それぞれの障害の番号を併合(加重)認定表に当てはめます。
例えば、右手の人差し指と親指の機能を失い、視力の良い方の視力が0.1になった場合、併合判定参考表からそれぞれの障害に番号を割り当て、併合(加重)認定表に当てはめると、2級と認定される可能性があります。
3つ以上の障害がある場合も同様です。
それぞれの障害に番号を割り当て、併合(加重)認定表を用いて、最下位の番号とその直近位の番号から順に併合番号を求めていきます。
最終的に算出された併合番号から障害等級が決定されます。
特例として、併合認定の結果に関わらず、国年令別表や厚年令別表に明示されている等級が優先される場合があります。
例えば、左下肢の5本の指を失った後に、右下肢の5本の指を失った場合、併合判定参考表ではそれぞれ8号-11に該当しますが、国年令別表の2級11号「両下肢の全ての指を欠くもの」に該当するため、併合認定の結果に関わらず2級と認定されます。
併合判定参考表の使い方
併合判定参考表には、様々な障害とその障害等級、そして併合認定における番号が記載されています。
ご自身の障害の状態と照らし合わせ、該当する番号を正確に特定することが重要です。
表の見方としては、まず障害の部位と状態を確認し、それに該当する番号を探します。
番号は障害の重さを表すもので、番号が小さいほど障害の程度が重く、等級が高くなる傾向があります。

併合認定の申請に必要な書類
診断書・意見書等の準備
申請に必要な書類は、障害の種類や原因によって異なります。
同一原因による障害の場合は、それぞれの障害種別に応じた診断書と病歴・就労状況等申立書が必要となるケースと、一枚の診断書と病歴・就労状況等申立書で済むケースがあります。
一方、異なる原因による障害の場合は、障害の種類ごとに診断書と病歴・就労状況等申立書に加え、受診状況等証明書も必要となる場合があります。
病歴・就労状況等申立書は、発病から初診までの経緯、受診状況、日常生活や就労状況などを記載する書類です。
受診状況等証明書は、障害の原因となった傷病の初診日を証明する書類です。
必要書類の提出方法
必要書類は、通常は年金事務所に直接提出するか、郵送で提出します。
オンライン申請の可否については、年金事務所にご確認ください。
提出前に、書類に不備がないか、事前に確認することが大切です。
申請書類のチェックリスト
申請書類のチェックリストを作成し、提出前に全ての書類が揃っているか確認しましょう。
チェックリストには、診断書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書など、必要な書類を全て列挙し、提出済みにチェックを入れていくことで、漏れを防ぐことができます。

障害年金併合認定の手続き
申請窓口と手続きの流れ
障害年金の申請は、お住まいの地域の年金事務所で行います。
手続きの流れは、まず申請に必要な書類を準備し、年金事務所に申請書を提出することから始まります。
その後、審査が行われ、結果が通知されます。
審査期間と結果通知
審査期間は、ケースによって異なりますが、数ヶ月かかることが一般的です。
結果通知は、郵送で送られてきます。
結果に納得できない場合は、不服申立てを行うことができます。
不服申立ての方法
審査結果に不服がある場合は、不服申立ての手続きを行うことができます。
不服申立ての方法や期限については、年金事務所の職員に確認しましょう。
不服申立てには、具体的な理由を明確に記載した書類の提出が必要になります。
まとめ
今回は、複数の障害を持つ方が障害年金を申請する際に有効な併合認定について解説しました。
併合認定は、複数の障害を個別に評価し、その重なりを考慮して障害等級を決定する方法です。
申請には、障害の種類や原因によって必要な書類が異なります。
診断書や病歴・就労状況等申立書に加え、場合によっては受診状況等証明書も必要になります。
申請手続きは年金事務所で行い、審査には数ヶ月かかる場合もあります。
審査結果に不服がある場合は、不服申立てを行うことができます。
併合認定は複雑な制度ですが、適切な手続きを行うことで、より高い等級で認定される可能性があります。
不明な点があれば、年金事務所や専門機関に相談することをお勧めします。
スムーズな申請に向けて、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

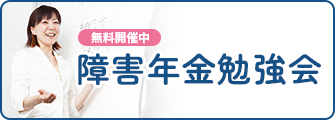


 初めての方へ
初めての方へ